うちの子がスマホ依存症になっているかも知れない、自分はスマホ依存になっているのではないか?と思う方はぜひ、このページを最後まで読んでみてください。
スマホは、いまや生活に欠かせない便利なツールとなっていますが、使い過ぎによって「スマホ依存症」に陥ってしまうリスクも高まっています。依存症とは何か?スマホに依存するとどんな危険性があるのか?詳しく解説していきます。
「依存する」とはどういうことなのか?
近年、スマートフォン(以下、スマホと呼びます)は急速に広まり、今や、子供も大人も高齢者も、持っていない人はほとんどいない、と言ってもいいぐらいに普及しています。そして、最も悪い影響を受けているのは、子どもです。スマホを使いすぎて、スマホを手放せなくなる、他のことが手につかない、夜更かしがひどくなり、勉強もろくにしなくなった・・・と、困り果てて、あわてて病院にかけつける親が増えています。これは誇張したものではなく、事実です。そして、未成年のスマホの使用について、政府が規制をかけない限り、その数はもっと増えていきます。
上記のように、スマホを手放せなくなるような人の症状を、スマホ依存、またはスマホ依存症と呼びます。正しくは、行為(ゲームなど)や人間関係に依存的になることを専門用語で「嗜癖(しへき)」といいますが、聞きなれない言葉なので、当ブログでは「依存症」と呼びます。
当ブログのサブタイトルでも記載していますが、筆者の息子も、スマホ依存の症状が出ており、不登校や引きこもりなどを経験していて、何としても、これらの問題を解決したいという願望があります。第一の願いはそれですが、日本いや世界中にも、同じようにスマホ依存から抜けられずに苦しんでいる子供らがいます。また、子どもだけでなく、大人になってから、スマホ依存に苦しむ人も大勢います。そういった人たちの助けになれば・・・と思って、スマホ依存症に関する記事を書いています。
話を戻します。
依存症とは・・・
まず、そもそも「依存する」とは、どういうことなのか?意外に認識があやふやな方が多いと思うので、ここで整理します。世界保健機関で作成された『国際疾病分類 第10回改訂版(ICD-10)(※)』によると、「依存症候群」とは「ある物質あるいはある種の物質使用が、その人にとって以前には、より大きな価値をもっていた他の行動より、はるかに優先するようになる一群の生理的、行動的、認知的現象・・・・」と記載があります。
※ICD-10(国際疾病分類第10版)とは、世界保健機関(WHO)が策定した、疾病や健康関連問題を分類・統計化するための国際的な基準のことです。
少し、わかりやすく言うと「他の大切なものよりも、ある物質の使用をはるかに優先する」ということです。例えば、仕事や学業よりも、ギャンブルやゲームなどを優先する、といったようにです。
依存症をよく知らない人は、これだけを見ると「スマホを使いすぎなければ問題ないんじゃないの?」と思うかも知れませんが、事はそう単純ではありません。
まず、人はどんなものにでも依存する訳ではありませんし、誰もが依存症になる訳でもありません。たとえば、カレーライスの好きな小学生はたくさんいますが、カレーライス依存症なんて言葉は、聞いたことがありません。親からすれば、受験生なら、試験勉強依存症になってくれたらいいのに・・・なんて妄想もあるかも知れませんが、残念ながら、これもありえません。依存症の対象となりえるものには、一定の条件があるのです。
依存症が発症する2つの条件
まず、依存する対象を「依存物」と定義します。依存物の第1の条件は、その物質や活動によって「快楽」がもたらされることです。「快楽」にはいろいろな表現がありますが、「楽しい」「すっきりする」「ワクワクする」「リラックスする」「くつろげる」「ハイになる」「刺激的だ」などが当てはまります。
そして、依存物の第2の条件は、「飽きがこない、飽きにくい、続けられる」ことです。
快楽を得られて、なおかつ、飽きずに続けられるモノ、それが依存症の対象となる可能性があるということになります。上記のカレーライスは、確かにおいしいですが何日も続くと、やがて飽きてしまって、依存する対象にはなりえません。受験勉強も飽きずに続けられたとしても、快楽を得られるような訳ではなく、これも依存する対象にはなりえません。依存症の対象となりえるものとして、挙げられるものは、お酒、パチンコ、タバコなどです。いずれも、快感を得られる、刺激が味わえる、そして、飽きずに続けられる可能性があります。
スマホや、ゲームなども、依存する対象物になりえます。他にもいろいろとありますが、まずは「依存症」という言葉について、お話しします。
スマホ依存症の人が増えていくカラクリ
どうして依存症が発症するのか、それが少し見えてきた訳ですが、では、どれぐらい、依存物を使いこめば、依存症と言える域にまで達するのでしょうか?もし、それがわかったとしたら、あと何回、お酒を飲めば、アルコール依存症になってしまうのかがわかって、リスクを回避できるかも知れません。しかし、依存症の発症には、個人的な因子が大きいことや、その人の置かれている状況や気分といったかなり複雑な因子が絡み合っているので、はっきりしたことがわかっていません(近い将来、研究によってこのあたりのことがわかるようになる可能性はあるかも知れませんが・・・)。違法薬物などを除いて、依存物を使用してすぐに依存症が発症することは稀なのです。
例えば、お酒を飲みすぎて、アルコール依存症になってしまうケースを考えてみます。お酒を飲み始めるのは20歳からの人が多いですが、アルコール依存症が問題化するのは、主に中高年です。20代のアルコール依存症というのは、稀に見られるものの、あまり多くありません。また、子どもたちがゲームを始めるのは、幼児~小学生低学年の頃が多いのですが、ゲーム依存症が重大な問題となるのは、中学生以降のことが多いようです。つまり、依存症が問題化するのは、依存物を使いだしてから、何年も後になってからというのが一般的なのです。だからこそ、身近にあるものの何が依存物なのかを知ることは、とてもとても重要なことなのです。筆者もこれがもっと早くにわかっていれば、長男にスマホを与えることを躊躇したし、もっと与える時を遅らせて、悲劇を回避できたかも知れません。
(ただ、子どもにスマホを与えなさすぎると、周りの子供らから仲間外れにされるのではないか、余計なストレスをかけ続けることになるのではないか?と親側の心配もよくわかります。しかし、筆者は小学生にスマホを与えることは百害あって一利なしと断言します。この話はまた別に行います)
依存症の正体
少し、説明っぽい話が続いていますが、スマホ依存のことを説明するのに重要な話なので、もうしばらくお付き合いください。ここで、依存症について、さらに深掘りしてみます。そもそも依存症の根幹となる症状は、「精神依存」と呼ばれるものです。
精神依存とはその名のとおり、「精神的に依存する」ことですが、これには「正の強化」と「負の強化」という2つの側面があります。アルコールや違法薬物などの物質依存症は脳内報酬系モデルから論じられるようになりましたが、ギャンブルやゲームなどの行為の依存症でも同様のことが起こります。
依存症の人が依存物を使用するのは、「快楽」を得るためという前提条件があります。快楽を得たい、気持ちよくなりたい・・・そのために依存物を使用することを『正の強化』といいます。しかし、この「正の強化」だけでは、依存症を理解したことになりません。
正の強化と負の強化
たとえば、依存症でない普通にゲームが好きな子供も、快楽を求めてゲームをしますし、依存症ではない普通に酒好きな人も、快楽を求めて酒を飲みます。つまり、多くの日常的な場面において、快楽を求めることも、快楽がなくなって我慢することもあります。特におかしなことではありません。しかし、依存症になると、依存物を止めてしまうと「不快」になります。この不快を解消するために依存物を使用することを「負の強化」と言います。
この「不快」は、「イライラする」「ムシャクシャする」「物足りない感じがする」「うつ」「不安」など様々な形で現れます。人は不快になると、その状態を解消しようとします。その手段はいろいろありますが、一般的に依存物でないものは「快楽」を得られても途中で飽きてしまったり、快楽を得るのが容易でないなどの特徴があります。
一方、依存物を使用中の「依存症である人」は、「依存症でない人」に比べて、総じて精神状態が悪い傾向にあることが知られています。これはスマホ依存症でも、アルコール依存症、インターネット・ゲーム依存症でも同様です。
しかし、ここで不可解なことが生じます。依存症の人は、依存物を使用するという「快楽」をたくさん得る行為をしているはずなのに、、なぜ、不快になってしまうのでしょうか?実際、楽しく遊びまわっている人は一見、幸せそうに見えます。しかしながら依存症の人は、依存物の使用によって快楽を得ても不快さが消えないという事態に陥ります。いくら依存物で「快楽」を得ようとしても、もともとの「不快」が強いせいで、なかなか解消されないのではないか?とも考えられますが、実はそうとはいえません。
依存症の人は、半端ではない量の依存物を使用していることが多くあります。たとえば、ゲーム依存症の人であれば、1日10数時間ゲームをプレイしているとか、アルコール依存症の人であれば、一日あたり日本酒一升(1.8L)の飲酒をするなどです(筆者も大学生時代に、ゲーム依存症となっていた時期があり、食事がどうでもよくなるくらいに、1日14~15時間ぐらいゲームをして、それが毎日続いていました。依存症になっている時は、とにかく半端ではない量をこなしています)。
これほど「快楽」を得る活動をしているにも関わらず、不快さはちっとも解消しておらず、むしろ不快さが増大するという、おかしなことが起こるのです。
快楽と不快の同時進行
結論からいえば、依存物は逆の作用をもたらします。つまり、依存症になってしまうと、快楽をもたらすはずの依存物を使えば使うほど、依存物を使っていないときの不快度は増してゆくのです。
人は快楽を得るために依存物を使います。快楽を得ることによって、より幸せになろうとします。ところが、依存物を使いすぎて依存症になると、依存物で快楽を得られる(正の強化)ものの「幸福」というゴールに至るのではなく、依存物を使わないときには、いつも不快(負の強化)が生じてしまうのです。
依存症の人はしばしば、依存物を使用する間は快楽を得られるので、それに満足して、より幸福感を得ようと使い続けます。しかし、同時に負の強化も進行していきます。そして、実際には、いつのまにか、自らが依存症の負の強化によって、「不快」になっていることに気づきにくくなるのです。
もちろん依存物をたくさん使用することによって、例えばアルコール依存症の場合、多量飲酒によって肝臓が悪くなる。ギャンブル依存症の場合にはお金がなくなる、人間関係が悪くなる。インターネット依存症やオンラインゲーム依存症の場合は学業成績が不振になるなど、依存症特有の悪影響によって「不快」になる場合もあります。それで、物理的に続けられなくなって、うまく依存症から脱する場合もありますが、肝臓が悪くても構わずお酒を飲む、お金がなくても借金してギャンブルをする、留年、退学して、そのままゲームをし続けるなど、強行する人もいます。筆者は運よく、大学を退学する代わりに、ゲーム依存症から脱することができましたが・・・。
普通は「快楽」を得ることを続けている人は幸せそうに見えますが、依存症になっている人の場合は、その逆のことが起きています。依存症者の場合、快楽をもたらす依存物を使えば使うほど、その人の不快度は次第に増していきます。依存症者にとっても、その周囲の人にとっても、依存物による「快楽を得られるけど不快になる」のを体感的に理解しにくいということが、この病の最もやっかいなところかもしれません。こうして依存症という病は重篤化してしまうのです。
スマホ依存症になる人の行動
依存症というものが、どのようにして発症していくのか、おわかりいただけたでしょうか。まだ、依存症になったことのない人にとっては、理解しづらい、想像しづらい話かも知れませんが、筆者を含め、依存症であった過去のある大人は案外、多いのではないかと思います。長い人生、いいこともあれば、つらいこともありますから。自分の病気を治すことも簡単ではありませんが、それ以上に、他者の病気を治すことは、もっと難しいと思います。その自覚がなかなか本人にはないかも知れませんが、依存症は病です。だから、依存している実態を理解しようとする姿勢はとても大事だと思います。その対象が家族なら、なおさらです。
実際にスマホに依存している人は、快楽を求めてスマホを使用します(正の強化)。はじめはほんとに軽い気持ちから始まる人がほとんどです。スマホゲームをちょっと遊んでみよう、その程度だったのが、いつのまにか、スマホゲームをやりすぎて、次第に依存症になると、スマホを使っていないと「不快」になります(負の強化)。その不快を解消するために、さらにスマホゲームで遊びます。これを繰り返しているうちに、スマホを使わないときの不快が強くなり、スマホから離れがたくなり、依存症が重症化していきます。まさに悪循環です。
実は、手を出してしまったあとも、スマホ依存にならないようにする策はいくつかあるのですが、子供のスマホ使用を、子供に任せっぱなしにして、放置していると、あっという間に、スマホ依存に陥ってしまいます。その子の精神の強さなどは、あまり関係ありません。
ですから、自分の子どもにスマホを与えるタイミングは、本当によく考えなくてはいけません。周りが持っているから、子どもが欲しいと言うから。そんな理由で、自分の子供を不幸にしても、後から取返しがつかないこともあります。子供にスマホを与えた後でも、成人するまでは、親が制御できるようにすべきです。時間制限や、アプリ制限など、いろいろ方法はあります。無策でスマホを与えてはいけません。
※一応、注意ですが、スマホ依存が重症化しているお子さんに対して、スマホをいきなり取り上げると、暴力をふるったり、突拍子もない行動をとったりするケースがあります(話し合いでうまく収まるケースもあるかも知れませんが)。依存症になっている人によって、取るべき対応は異なってきます。どう対応すべきか、医師に相談するのが一番だと思います。
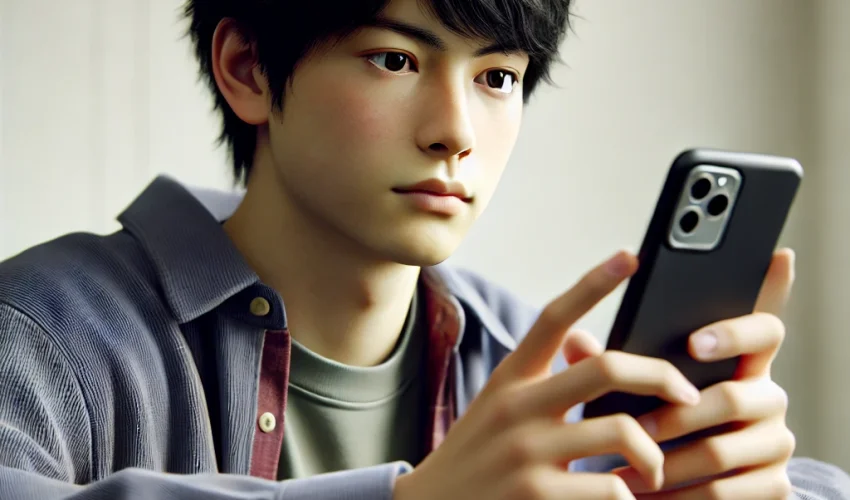






この記事へのコメントはありません。